※当ブログはアフィリエイト広告を利用しています。

「敬老の日って何歳から祝うの?」そんな素朴な疑問を持ったことはありませんか?
高齢者を敬い感謝を伝えるこの祝日ですが、実は年齢の定義があいまい。
そこで今回は、何歳から祝うべきなのかという基本から、現代のライフスタイルに合ったお祝いの仕方、喜ばれるプレゼントやマナーまで、敬老の日をもっと深く理解できる情報をたっぷりお届けします。
大切な人に「ありがとう」を伝える参考に、ぜひ最後までご覧ください。

目次
敬老の日の対象って何歳から?その定義を徹底解説
法律では決まっているの?
実は「敬老の日」が何歳からという明確な年齢の定義は、日本の法律にはありません。祝日法(国民の祝日に関する法律)では、「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日」とされているだけで、具体的な年齢の線引きは書かれていないのです。
そのため、「何歳から祝うのか?」という疑問には、明確な正解が存在しません。これは地域や家庭によって異なり、「還暦(60歳)を迎えたら対象になる」という考え方もあれば、「孫ができて初めて敬老の日の対象になる」という声も多くあります。したがって、敬老の日の対象を決める際は、本人の気持ちや家庭の考え方を尊重するのが一番のポイントになります。
世間一般の年齢の目安は?
多くの人が気になる「一般的には何歳から敬老の日の対象になるのか?」という点については、いくつかの調査や意見があります。例えば、内閣府や自治体が行っている敬老の日の記念事業では、70歳以上の方を対象にしているケースが多く見られます。
また、地域の敬老会や高齢者向けの祝い行事では「65歳以上」が対象となっていることが一般的です。これは、厚生労働省などの高齢者に関する定義が「65歳以上」であることに由来しています。ただし、実際に家庭の中でお祝いする際には「60歳の還暦」をきっかけに敬老の日に祝うことが多く、その後は毎年祝うようになる家庭もあります。
60歳・65歳・70歳…どこで線引きするの?
「どのタイミングで敬老の日を祝うか?」は悩ましい問題ですが、実際には以下のような年齢を目安にする人が多いです。
| 年齢 | お祝いされる理由 |
|---|---|
| 60歳 | 還暦(干支が一巡)を迎える年齢として祝われることが多い |
| 65歳 | 定年退職・年金受給開始の年齢として意識される |
| 70歳 | 「古希」としての節目であり、地域イベントでも対象となりやすい |
このように、それぞれの年齢に「節目」があるため、家庭や地域によって祝うタイミングが異なるのです。中には「70歳を過ぎてからでいい」と考える人もいれば、「60歳になったらもう立派な敬老対象」と思う人もいます。
実際に敬老の日に祝われる人の声
実際に敬老の日にお祝いされている60代〜70代の人たちに話を聞いてみると、反応はさまざまです。「孫からの手紙や似顔絵は何より嬉しい」と喜ぶ方もいれば、「まだそんな年じゃないのに」とちょっと戸惑う方もいます。
特に60代の若々しいシニア世代は、まだまだ現役で働いている人も多く、「敬老」と言われることに違和感を感じることも少なくありません。一方、孫の存在がきっかけで初めて敬老の日を実感するという人もいて、「自分が年をとったことを実感するけど、悪い気はしない」と微笑む声もあります。
年齢ではなく“孫がいるか”がポイント?
最近では、「年齢よりも“孫ができたかどうか”で判断する」という考え方も増えています。これは、孫からのプレゼントや手紙がきっかけで「敬老の日の対象になった」と実感する人が多いためです。つまり、形式的な年齢よりも“ライフステージ”が重要視されているのです。
例えば、50代でも早くに孫ができた人は祝われることがありますし、逆に70歳を超えていても子どもにまだ孫がいなければ祝われないこともあります。家族の事情に合わせて柔軟に考えるのが、現代の「敬老の日」の新しいスタイルかもしれません。
お祝いする側が知っておきたいマナーと気配り
祝うタイミングは?当日?前日?
敬老の日をいつ祝うべきかというと、基本的には祝日である「敬老の日」(9月の第3月曜日)に行うのが一般的です。ただ、家族の都合や本人のスケジュールもあるため、実際には前の週末やその前後の休日に祝う家庭も多くあります。
特に遠方に住んでいる場合は、連休を使って会いに行くこともあるでしょう。重要なのは「日にち」よりも「気持ち」で、当日にこだわる必要はありません。また、仕事や学校の都合で当日に祝えない場合でも、事前に手紙や電話を送るだけでも、心のこもったお祝いになります。
喜ばれる言葉やメッセージとは?
敬老の日には感謝やねぎらいの言葉を伝えるのが大切です。形式ばったメッセージよりも、「いつもありがとう」「元気でいてね」といったシンプルな言葉が心に響きます。もし手紙やメッセージカードを添えるなら、孫からのメッセージが特に喜ばれます。
イラストや似顔絵を添えるのも良いですね。大切なのは、「年寄り扱いする」ような言い方を避けることです。「まだまだ若々しいね」「一緒に出かけようね」といった前向きな言葉を選ぶと、相手にとっても嬉しい気持ちになります。
年齢に敏感な人への配慮の仕方
最近では60代や70代でもアクティブに活動している人が多いため、「敬老」という言葉に抵抗を感じる人もいます。そのため、お祝いする際には相手の気持ちに配慮しましょう。「敬老の日だからお祝いしてあげる」ではなく、「いつもありがとうの気持ちを込めて」といった柔らかい伝え方がベストです。
特に女性の場合、年齢を強調するのは避けた方がよいでしょう。プレゼント選びでも「老眼鏡」や「杖」といった“老い”を感じさせるものは避け、趣味や好みに合ったアイテムを選ぶのがポイントです。
プレゼント選びでやってはいけないこと
プレゼントを選ぶときには、「実用的だから」と安易に高齢者向けグッズを選ぶのは危険です。たとえば、健康器具や介護用品などは相手によっては失礼に感じることもあります。特に、「もう年だから」といったニュアンスが伝わってしまうと、お祝いのつもりが逆効果になることも。
相手の趣味や生活スタイルに合わせて、「もらって嬉しい」と思ってもらえるものを選びましょう。最近では、体験型ギフトや食事券なども人気があります。形よりも気持ちが伝わる贈り物が大切です。
直接会えないときの気持ちの伝え方
遠方に住んでいたり、忙しくて直接会いに行けない場合でも、お祝いの気持ちは伝えられます。電話やビデオ通話はもちろん、手紙やポストカードも喜ばれます。また、最近はLINEやメールで写真や動画メッセージを送る人も増えています。
孫の成長の様子や、家族で作った料理の写真などを添えると、より温かい気持ちが伝わるでしょう。プレゼントを宅配で送る際も、一言メッセージを添えるだけで印象が大きく変わります。会えない距離を、気持ちで埋めることが大切です。
敬老の日におすすめのプレゼントはコレ!
定番人気ランキングベスト5
敬老の日に贈るプレゼントは、やはり「気持ちが伝わること」が大切です。以下に、近年特に人気のあるプレゼントをランキング形式でご紹介します。
| ランク | プレゼント | 理由 |
|---|---|---|
| 1位 | 孫の写真・手紙・似顔絵 | 何よりも「家族の想い」が伝わる |
| 2位 | 花束やフラワーギフト | 見た目が華やかで季節感がある |
| 3位 | お菓子・グルメギフト | 好みが分かりやすく、すぐ楽しめる |
| 4位 | マッサージグッズ・健康家電 | 癒し系で喜ばれることが多い |
| 5位 | 体験ギフト・食事券 | 思い出作りができる贈り物として注目 |
特に「孫からの贈り物」は、物の価値以上に心に響くものがあります。
自分のために時間をかけてくれたことが伝わるので、最も喜ばれる傾向があります。
\定番から予算別など選び方いろいろ/
孫からの手作りプレゼントが喜ばれる理由
年配の方にとって、孫は宝物のような存在です。その孫が一生懸命作った絵や工作、手紙などは、お金には代えられない価値があります。たとえば、折り紙で作った花や手書きのメッセージカードなどは、小さなお子さんでも簡単に作れます。
保育園や小学校でも「敬老の日」に向けて工作をすることがあるため、それを贈ると非常に喜ばれます。作品には「ありがとう」「だいすきだよ」などの言葉を添えると、さらに感動されること間違いなしです。手作りならではの温もりが伝わるので、ぜひおすすめしたいプレゼントの一つです。
高齢者向けの健康グッズや家電も人気
年齢を重ねるにつれて、健康への関心が高まるのは自然なこと。そこで、健康をサポートするグッズや家電製品は敬老の日のプレゼントとしても人気です。例えば、家庭用マッサージ器や電動足湯機、温熱パッドなどは、日常的に使えるアイテムとして喜ばれます。
ただし、「年を取ったから必要でしょう」といったニュアンスを含まないように、あくまで“癒し”や“快適さ”を意識した選び方が大切です。メッセージカードに「いつも元気でいてね」などの言葉を添えることで、ポジティブな印象を与えることができます。
失敗しないお菓子や食品の選び方
グルメギフトは、もらってすぐ楽しめるため、敬老の日にも多く選ばれています。ただし、年配の方は「歯が弱い」「塩分や糖分を控えている」などの健康上の制限があることも少なくありません。そこで、柔らかい食感のお菓子(ようかん、プリン、ゼリーなど)や、減塩・無添加の食品ギフトが安心です。
また、和菓子や地元の名産品など、懐かしさを感じるようなアイテムもおすすめです。「この前旅行した時に美味しかったから…」というエピソード付きで渡すと、より心のこもった贈り物になります。
経験を贈る:旅行・食事券のすすめ
最近人気が高まっているのが、「モノより思い出」を大切にした“体験型ギフト”です。たとえば、高級レストランの食事券や温泉旅館の宿泊チケットなどは、「一緒に過ごす時間」を贈れる素敵な選択肢です。
特に一人暮らしの高齢者や、普段なかなか外出の機会が少ない方には喜ばれます。日帰りバスツアーや地元の観光体験チケットなど、気軽に楽しめるプランも豊富です。
体験ギフトを選ぶ際は、無理のないスケジュールで移動距離も考慮して選びましょう。
「家族で楽しむ敬老の日の過ごし方アイデア」
みんなで写真撮影&アルバム作成
敬老の日におすすめなのが、「家族写真を撮ること」です。最近はスマートフォンでも高画質な写真が撮れるので、プロに頼まなくても十分思い出に残る一枚が残せます。撮った写真はプリントしてアルバムにしたり、フォトブックを作ったりすると、プレゼントとしても喜ばれます。
過去の家族写真と一緒に「成長記録」や「思い出ストーリー」を入れて贈るのもいいですね。家族全員が集まって写真を撮るだけでも、相手にとっては何よりの贈り物になります。
手料理パーティーで感謝の気持ちを表現
「お祝い=ごちそう」というイメージも強いため、家族みんなで手料理を囲むのも素敵な過ごし方です。おばあちゃん・おじいちゃんの好きな料理を中心にメニューを考えたり、孫と一緒に料理を作ったりすると、準備段階から楽しめます。
お寿司や煮物、お吸い物といった和食を中心に、ヘルシーで食べやすいメニューを選ぶと安心です。また、手作りのメニュー表を作ってレストラン風に演出するのも人気です。食卓に感謝の気持ちが自然と広がります。
敬老の日向けのイベント・レクリエーション
地域によっては、敬老の日にあわせたイベントが開催されることもあります。たとえば、町内会や自治体の敬老会、地域の集会所での演奏会やカラオケ大会、ビンゴ大会などが人気です。
これらのイベントに参加することで、同世代との交流が生まれ、気分転換にもなります。お孫さんが学校や保育園で練習した歌やダンスを披露する“ファミリーイベント”もおすすめ。家庭内でも、クイズ大会や昔の思い出話をする時間を作ると、笑顔が絶えない時間になります。
一緒に散歩や温泉でゆったり過ごす
忙しい日常の中で、静かな時間を一緒に過ごすことも大切です。近所の公園を散歩したり、少し足を伸ばして温泉に行ったりすると、リラックスした時間を共有できます。
温泉は、体を温めるだけでなく、非日常を味わえるため、気分転換にもぴったりです。バリアフリーに対応した施設も増えており、高齢の方でも安心して利用できます。また、途中の道の駅やサービスエリアでの休憩も、ちょっとした楽しみになります。一緒に過ごすことで、心の距離もぐっと近づきます。
オンラインでもできる!リモートお祝い術
遠方に住んでいてなかなか会えない場合でも、リモートでの「お祝い」が可能です。ZoomやLINEビデオ通話を使って「オンライン敬老の日」を開く家庭も増えています。
あらかじめプレゼントや手紙を送っておいて、通話でその場で開けてもらうと感動も倍増。孫の歌やピアノ演奏を見せたり、思い出の写真をスライドショーにして共有するのもおすすめです。オンラインでも十分気持ちは伝わる時代。顔が見えるだけで、きっと喜んでくれるはずです。
今どきの敬老の意味と世代間ギャップ
若々しい60代・70代が増えている現実
現在の60代・70代は、昔に比べてとても若々しく、元気な人が多いです。スポーツジムに通ったり、旅行や趣味を楽しんだりと、いわゆる「高齢者」とは感じられない方も少なくありません。
見た目や体力だけでなく、SNSを使いこなす方や、シニア起業をする人も増えていて、「敬老=お年寄り」というイメージは、すでに過去のものになりつつあります。
だからこそ、形式的な敬老ではなく、相手のライフスタイルに合った感謝の伝え方が求められる時代です。
「敬老」と呼ばれることへの抵抗感
「敬老の日にお祝いされたけど、ちょっと複雑だった」という声もよく聞かれます。特に60代前半では、「まだそんな年じゃないのに」と感じる人も多く、「敬老」という言葉自体に抵抗を持つ人もいます。
こうした声を無視して一方的に祝ってしまうと、逆に距離を感じさせてしまうことも。だからこそ、言葉選びや伝え方には細心の注意が必要です。「お疲れ様です」「いつもありがとう」といったフラットな表現を選ぶだけでも、印象はずいぶん変わります。
新しい呼び方や祝い方のアイデア
「敬老」という言葉に代わる、新しい呼び方や祝い方も登場しています。たとえば、「ありがとうの日」「家族感謝の日」「おつかれさまの日」など、ポジティブな響きを持つ名前に変える家庭もあります。
また、お祝いも「パーティー」や「旅行」といった“楽しいイベント”として演出することで、年齢を意識させず自然に祝うことができます。大切なのは、年齢ではなく「感謝の気持ち」をどう伝えるかです。相手にとって心地よいスタイルを選びましょう。
世代間のコミュニケーションの工夫
世代が違うと、価値観や言葉の使い方にギャップが生まれがちです。例えば、若者が使うカジュアルな表現が高齢者には伝わりにくいこともあります。
だからこそ、日頃から会話を大切にし、相手の趣味や関心を理解する努力が必要です。また、昔の話を聞いてみるのもいい方法です。「昔どんな遊びをしていたの?」「どんな仕事をしていたの?」といった質問を投げかけると、会話が弾みます。こうした対話の積み重ねが、敬老の日をより豊かな時間にしてくれます。
これからの敬老の日のあり方とは?
少子高齢化が進む日本において、これからの敬老の日の過ごし方も変わっていくでしょう。今後は「年齢」ではなく、「人生経験」や「家族との関わり方」に重きを置いた形での祝福が主流になるかもしれません。また、多様な家族構成の中で、それぞれのライフスタイルに合った自由な祝い方が求められる時代です。「これが正解」という形はないからこそ、相手を思う気持ちを大切にしながら、自分たちらしい敬老の日を創っていきたいですね。
まとめ
敬老の日は、年齢や形式にとらわれず、感謝の気持ちを伝えることが最も大切です。「何歳から祝うか」という疑問に正解はなく、それぞれの家庭の考え方や相手の気持ちに合わせた祝い方が求められます。
プレゼント選びや過ごし方にも工夫を凝らし、心のこもった1日にすることが、何よりの“贈り物”となるでしょう。世代を超えたつながりを感じられる日として、これからも大切にしていきたいですね。
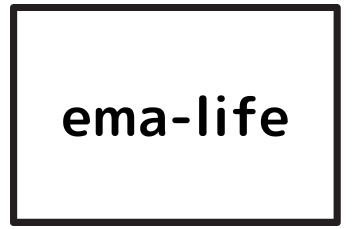

コメント