※当ブログはアフィリエイト広告を利用しています。
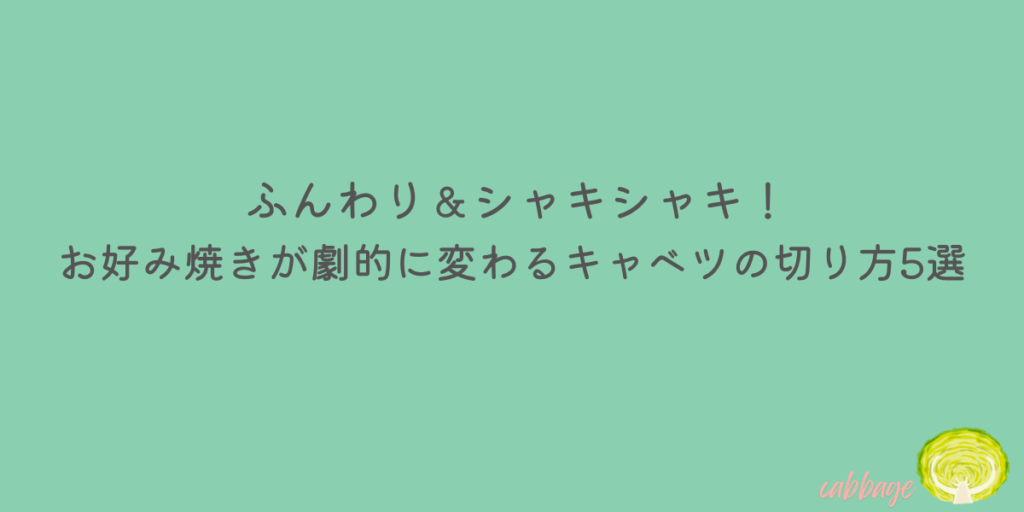
「お好み焼きはキャベツで決まる」って聞いたことありませんか?
ふわっと軽い仕上がり、シャキシャキの食感、しっかり甘みのある味わい――そのすべてはキャベツの“切り方”にかかっているんです!
実は、キャベツはただ切って入れるだけではもったいない。包丁の入れ方、厚み、大きさによって仕上がりはガラッと変わります。この記事では、料理好きならぜひ知っておきたい「キャベツの切り方テク」を徹底解説!
プロの料理人も実践するコツから、家庭で失敗しない方法、さらにはキャベツの栄養を逃さず使い切る保存術まで、まるっとご紹介します。
読むだけで、あなたのキャベツの使い方が劇的に変わるかも!
目次
お好み焼きの味を左右するのはキャベツの切り方だった!

千切り?粗みじん?プロが使う切り方とは
お好み焼きの美味しさは、実はキャベツの切り方で大きく左右されるって知っていましたか?ふわっと仕上げたいのか、しっかり食感を出したいのか、目指す仕上がりによってベストな切り方が違います。家庭ではあまり意識しないかもしれませんが、プロの鉄板焼き屋さんやお好み焼き専門店では、キャベツの切り方にかなりこだわっています。
例えば「千切り」は、細く均一に切ることでキャベツの水分が出にくく、焼いたときに空気を含みやすくなるため、ふんわり軽い口当たりになります。これが関西風お好み焼きに向いている理由です。一方、「粗みじん切り」は、キャベツの食感をしっかり残すことができ、広島風お好み焼きのように層を作って焼くスタイルに適しています。
包丁の入れ方ひとつで火の通り方も水分の出方も変わってくるので、「どんなお好み焼きを作りたいか」を考えてキャベツの切り方を選ぶと、仕上がりに大きな違いが出ます。プロの料理人は、キャベツの芯と葉を分けて、それぞれ別の切り方をすることもあるんですよ。
キャベツの切り方を変えるだけで、まるで別の料理のように感じられることも。次にお好み焼きを作るときは、ぜひこの違いを試してみてください。
切り方ひとつで変わる「ふんわり感」と「食感」
お好み焼きにおけるキャベツの役割は、「生地をふんわりさせること」と「シャキッとした食感を加えること」の2つがあります。この2つのバランスを左右するのが、まさにキャベツの切り方なのです。
細い千切りにすると、キャベツの繊維が断たれやすくなり、火が通りやすくなります。そのため、生地が膨らみやすく、ふんわり軽い仕上がりになります。ただし、あまりにも細すぎると水分が出すぎて逆効果になることもあるので、1〜2mm程度を目安にカットするのがコツ。
逆に粗みじん切りにすると、キャベツの繊維がそのまま残るため、シャキッとした食感が楽しめます。この食感が好きな人にはたまらないポイントですが、生地が重くなってしまう可能性があるため、具材の量や生地の量とのバランスも大事です。
つまり、「ふんわり重視なら千切り」「食感重視なら粗みじん」が基本の考え方。自分の好みや、その日の気分で使い分けることで、家庭のお好み焼きのレベルがグンと上がりますよ。
火の通り方が変わる!厚みと大きさのバランス
キャベツの切り方を考えるうえで見逃せないのが「厚み」と「大きさ」のバランスです。お好み焼きを均一に焼き上げるには、キャベツの切り方が非常に重要なんです。
まず、厚みがあると中心まで火が通るのに時間がかかり、焼きムラの原因になります。外は焦げているのに中は半生……なんて失敗もよくある話。それを防ぐためには、1cm未満の幅で均一に切ることがポイント。均一な厚さであれば、全体にムラなく火が入りやすく、焼き時間の目安も立てやすくなります。
さらに、キャベツの大きさにも注意。大きすぎると混ぜづらくなり、生地との一体感が失われます。逆に小さすぎても食感がなくなってしまいます。目安としては、ひとくちサイズよりやや小さめくらいがちょうど良いです。
プロの料理人は「火の通り」「水分量」「食感」の3つを同時にコントロールしています。そのベースになるのが、まさに切り方の工夫なのです。
時短でも美味しく!手早く切るコツ
忙しい日でも美味しいお好み焼きを食べたいですよね。キャベツを手早く、それでいて適切な大きさに切るにはちょっとしたコツがあります。包丁の入れ方、持ち方、まな板の使い方を工夫するだけで、時短が実現します。
まず、キャベツは芯を取り除いてから切るのが鉄則です。芯があると切りづらく、包丁も滑りやすくなって危険です。芯を切り取ったら、葉を3〜4枚ずつ重ねて巻き、端から細く切っていくと千切りが一気にできます。
粗みじんの場合は、キャベツをざっくりと数センチ幅に切ってから、縦横に包丁を入れるようにします。このときも、まな板に対して垂直に包丁を下ろすとムラが出にくくなります。
時短のポイントは「切り方のパターンを決めておくこと」。迷わずに一定のリズムで切ることで、時間もかからず美しく仕上がりますよ。慣れてきたら、包丁ではなくスライサーを活用するのもおすすめです。
間違えるとベチャっとする!?NGな切り方とは
せっかくのお好み焼き、焼き上がったら「なんだか水っぽい」「ベチャっとしてる」…そんな経験ありませんか?それ、もしかしたらキャベツの切り方が原因かもしれません。
一番やってはいけないのが、切った後に水洗いしてそのまま使うこと。キャベツは水分を多く含んでいるので、洗ったあとはしっかり水気を切らないと、生地の中で水が出てしまい、焼いても焼いても中がベチャベチャになります。
また、あまりにも細かく切りすぎるのもNG。水分が出やすく、火の通りは早くなっても、生地が重くなり、ふんわり仕上がりません。特にスライサーで極細にしすぎると、水分がドバッと出る原因に。
切った後のキャベツは、キッチンペーパーで軽く押さえるか、ざるに広げて10分ほど置いておくと余分な水分が抜け、焼いたときにちょうど良い状態になります。
つまり、美味しいお好み焼きは「切り方」だけでなく「切ったあとの扱い」まで含めて工夫することが大切なのです。
切り方別!お好み焼きの仕上がり比較
千切りキャベツのふんわり仕上げ
キャベツを千切りにすると、お好み焼きの仕上がりは「ふんわり」と軽くなります。これはキャベツの断面が細くなることで、生地とよく絡み、火の通りも早くなるためです。また、千切りにすることで生地全体に空気が入りやすくなり、焼いたときにふっくら膨らむのです。
特に関西風のお好み焼きでは、キャベツの千切りが定番です。ふんわり仕上げたい場合は、キャベツの葉を数枚重ねてくるくると巻いてから、端から細く切っていく方法がおすすめ。1〜2mm程度の太さを目指すと、ほどよく火が入り、口当たりが柔らかくなります。
ただし、細すぎると水分が出やすくなるので注意が必要です。切った後に軽く水分を拭き取る、もしくはしばらく置いて水を切ることでベチャっとするのを防げます。
また、千切りキャベツは生地にしっかりと絡むため、焼いている間に具材がバラけにくく、ひっくり返しやすいという利点もあります。初めてお好み焼きを作る人や、子どもと一緒に作る場合にもおすすめの切り方です。
粗みじんの食べ応えと甘みの違い
キャベツを粗みじん切りにすると、焼き上がったときの「シャキシャキ感」や「甘み」がしっかりと感じられるのが特徴です。特に広島風お好み焼きやボリュームを出したいときに向いています。
粗みじんにすることで、キャベツの細胞が壊れすぎず、加熱してもシャキッとした歯ごたえが残ります。また、加熱時間が長めになることで、キャベツ本来の甘みが引き出され、全体の味わいがぐっと深まります。
切り方の目安は、1cm角より少し小さいくらいがちょうど良いサイズ。大きすぎると火が通りにくく、小さすぎると水分が出やすくなるので注意が必要です。
粗みじんにしたキャベツは、全体に散らすのではなく、生地の中央にまとめて入れると、食べたときにボリューム感が出て満足感が高まります。噛みごたえのあるお好み焼きを求める方にはぴったりのスタイルです。
包丁の入れ方で水分量が変わる?
実は、キャベツの切り方だけでなく、「包丁の入れ方」でも水分量が変わるって知っていましたか?これを知っているかどうかで、お好み焼きの仕上がりがかなり変わってきます。
キャベツの葉は繊維が縦に走っているため、この繊維を横切るようにカットすると、繊維が壊れて水分が出やすくなります。反対に、繊維に沿って縦に切ると、繊維が壊れにくく、水分があまり出ません。
そのため、「水っぽさを避けたい」「シャキシャキ感を残したい」というときは、繊維に沿って切るのがコツです。一方で、ふんわり感を出したいときは、あえて繊維を断ち切るようにカットすることで、火の通りが良くなり、生地がふくらみやすくなります。
つまり、仕上がりに合わせて「縦切り」か「横切り」かを選ぶのがプロの技。キャベツを切るとき、ただ刻むのではなく、「どう仕上げたいか」を意識しながら包丁を入れると、お店のような仕上がりに近づけますよ。
子どもに人気のキャベツの切り方
子どもと一緒にお好み焼きを楽しむなら、キャベツの切り方にも少し工夫を。子どもは食感に敏感で、「シャキシャキしすぎる」「大きすぎる」と食べてくれないこともあります。
そんなときにおすすめなのが、「細かめの千切り+軽いみじん切り」のハイブリッド。柔らかく仕上がる千切りをベースに、少し細かめに刻んであげることで、ふんわり感と食べやすさの両方が手に入ります。
また、キャベツの芯は固くて嫌がる子が多いため、芯の部分は取り除いて葉の柔らかい部分だけを使うと良いでしょう。苦みも少なく、甘みが出やすいのもポイントです。
さらに、お好み焼きをカットする前に小さく刻んだキャベツが入っていれば、子どもが食べやすくなるだけでなく、偏食対策にもなります。食物繊維やビタミンがしっかり摂れるので、栄養面でも◎。
「キャベツが嫌いだった子どもが、これならパクパク食べた!」という声も多い、家庭向けの工夫です。
プロの鉄板焼き屋が実践するスタイル
お店で食べるお好み焼きって、どうしてあんなに美味しいんだろう?と思ったことはありませんか?その秘密のひとつが、プロのキャベツの切り方にあります。
鉄板焼き屋さんでは、キャベツを芯と葉で分けて切ることがよくあります。芯の部分は硬くて火が通りにくいため、薄くスライスするか、粗くみじん切りにして火が入りやすいようにします。葉の部分はふんわりさせるため、千切りにして軽く空気を含ませながら混ぜるのが鉄則です。
また、切ったあとのキャベツを「室温でしばらく寝かせておく」こともあります。これは余分な水分を出させて、生地の仕上がりがベチャっとならないようにするため。まさにプロの一手間です。
さらに、混ぜ方にもポイントがあります。キャベツと生地を「練らずに混ぜる」。これによってキャベツが潰れず、空気を含んだままふんわりとした食感になります。
家庭でもこのプロの技を取り入れるだけで、ワンランク上のお好み焼きが楽しめますよ。
キャベツの切り方で栄養も変わる?
ビタミンCが逃げにくい切り方とは
キャベツにはビタミンCや食物繊維がたっぷり含まれていて、体にもとても良い野菜です。でも、切り方や加熱方法によっては、その栄養が減ってしまうこともあるんです。特にビタミンCは水に溶けやすく、熱に弱いので、切り方に注意が必要です。
ビタミンCをなるべく逃さないようにするには、キャベツの繊維に沿って切るのがポイント。繊維に沿って切ることで細胞が壊れにくくなり、栄養素が外に出にくくなるからです。逆に繊維を断ち切るように切ると、細胞が壊れて水分やビタミンが流れ出てしまいます。
また、切ったキャベツを水にさらしすぎるのもNG。見た目はシャキッとしますが、水にビタミンCが溶け出してしまいます。洗うときはさっと軽く水を通す程度にとどめ、しっかり水気を切るようにしましょう。
さらに、切ったあとのキャベツは時間が経つほど栄養が減ってしまうので、できるだけ早めに使うのがおすすめです。つまり、栄養をしっかり取りたいなら、「繊維に沿って切って」「洗いすぎず」「すぐ使う」のが鉄則です。
繊維を断つ?活かす?迷ったらコレ
キャベツを切るとき、「繊維に沿って切るか」「断ち切るか」で迷う人も多いですよね。それぞれにメリットがあるので、仕上げたい料理のスタイルに合わせて使い分けるのがコツです。
繊維を断つ切り方(横切り)は、火の通りが早く、ふんわりした食感に仕上がります。お好み焼きのように短時間で焼き上げたい料理にぴったりです。また、柔らかくなるので子どもや高齢の方にも食べやすいというメリットがあります。
一方、繊維を活かす切り方(縦切り)は、シャキシャキとした食感が残りやすく、炒め物やスープに向いています。水分も出にくいため、べちゃつかずに仕上がるのがポイントです。
迷ったときは、「柔らかくしたい→繊維を断つ」「食感を残したい→繊維に沿う」と覚えておけばOK。切り方を変えるだけで、同じキャベツでも全く違う料理になりますよ。
切った後の保存方法も大事!
せっかくきれいに切ったキャベツ、余ったらどうしていますか?保存方法を間違えると、せっかくのシャキシャキ感や栄養がどんどん失われてしまいます。
まず大事なのは、「空気に触れさせないこと」と「水分を適度に保つこと」。キャベツは空気に触れると酸化して、変色や栄養の劣化が進みます。切ったらすぐにラップで包むか、ジッパー付きの保存袋に入れて冷蔵庫に入れましょう。このとき、できるだけ空気を抜くのがポイントです。
さらに、乾燥を防ぐために、少し湿らせたキッチンペーパーで包むと長持ちします。これで2〜3日はシャキッとしたまま保存できます。
もし大量に切ってしまった場合は、冷凍保存も可能です。ただし、冷凍すると食感が変わるため、お好み焼きなど火を通す料理に使うのが◎。冷凍する際は、あらかじめ1回分ずつ小分けにしておくと便利です。
保存方法を工夫すれば、忙しい日の時短にもなりますよ。
キャベツの芯は使う?捨てる?
キャベツの芯、皆さんはどうしていますか?「硬いから捨てる」という人も多いかもしれませんが、実は芯にも栄養がたっぷり詰まっているんです。食物繊維やビタミンC、カリウムなどが豊富で、むしろ葉より栄養価が高いともいわれています。
ただし、そのままだと硬くて食べにくいのも事実。そこでおすすめなのが、「薄切り」や「みじん切り」にして使う方法です。お好み焼きに入れるときは、芯だけをみじん切りにして生地に混ぜ込むと、自然に火が通って柔らかくなり、違和感なく食べられます。
また、芯はスープや炒め物に使うと、ほんのり甘みが出て美味しくなります。特にコンソメスープにすると旨みが引き立ち、栄養満点のおかずになりますよ。
キャベツの芯を上手に使えば、食品ロスの削減にもなりますし、家計にもやさしい。これを機に、「芯まで食べる派」に変わってみてはいかがでしょうか?
一番栄養を活かせる調理タイミング
キャベツの栄養をできるだけ無駄なく摂るには、「切るタイミング」と「加熱のタイミング」も重要です。ビタミンCなどの水溶性ビタミンは空気や水、熱に弱いため、調理の直前に切るのがベストです。
たとえば、朝にまとめて切って冷蔵庫に入れておくよりも、使う直前に切るほうが栄養を逃しにくいです。もし前もって切っておくなら、ラップできっちり包んで空気に触れないようにしましょう。
加熱時間もポイントです。ビタミンCは熱に弱いため、長時間加熱するとどんどん減ってしまいます。お好み焼きのように短時間で焼く料理は、実はキャベツの栄養をしっかり残しやすい調理法なんです。
つまり、栄養を活かすには「調理直前に切る」「火は短時間で通す」が基本。ちょっとした意識の差で、キャベツの栄養をムダなく美味しくいただくことができます。
お好み焼き以外にも使えるキャベツの切り方テク
サラダにも応用!シャキシャキ千切り
キャベツの千切りはお好み焼きだけでなく、サラダにも大活躍します。ポイントは「とにかく細く、均一に切ること」。これによって口当たりが柔らかくなり、ドレッシングの絡みもよくなるんです。
サラダ用の千切りは、お好み焼きよりもさらに細め、1mm以下を目指すのが理想。細くすることでキャベツの繊維がより断ち切られ、しっとり感が出て食べやすくなります。スライサーを使うのも時短になっておすすめですが、包丁でもコツを掴めば十分可能です。
また、切ったあとに氷水に5分ほどさらすと、キャベツがシャキッと復活して食感が格段に良くなります。さらしたあとはしっかり水気を切るのが大事。水が残っているとドレッシングが薄まり、味がぼやけてしまいます。
冷蔵庫で冷やすとさらに美味しさアップ!和風、洋風、アジア風とどんなドレッシングにも合うので、常備しておくと便利ですよ。
スープ用にはこの切り方がおすすめ
スープやポトフにキャベツを入れると、甘みが溶け出してとても美味しいですよね。そんなときにおすすめの切り方は「ざく切り」。葉を大きめにざっくりと切ることで、煮込んでも形が崩れにくく、スープの中でも存在感がしっかりと残ります。
具体的には、キャベツを4〜5cm角くらいのサイズにカットするのがベスト。あまり小さく切ると、煮ているうちにクタクタになりすぎてしまい、歯ごたえがなくなってしまいます。
また、芯の部分もスープには最適。じっくり煮込むと甘みが出て、だし代わりにもなります。芯はスライスして一緒に煮込むだけでOK。
カレーやミネストローネ、味噌汁に入れるときもこの切り方が応用できます。キャベツを煮込むことでスープに自然なとろみが加わり、優しい味わいになりますよ。
炒め物で味がしみやすくなる切り方
炒め物にキャベツを使うときは、「大きすぎず小さすぎない、繊維に沿ったざく切り」がおすすめです。炒める料理では火の通りと味の染み込みが重要なので、切り方ひとつで仕上がりが全く違ってきます。
まず、繊維に沿ってカットすることで、加熱してもキャベツの形がしっかり残り、シャキシャキした食感が保てます。また、調味料が絡みやすい面積になるため、味もしっかりしみ込みます。
カットの目安は、幅2cm・長さ4〜5cmほどの短冊切り。炒めているうちにちょうどよくしんなりし、肉や他の野菜ともよく馴染みます。
さらに、炒める順番にもコツがあります。キャベツは最後にサッと炒めるのが基本。火を入れすぎると水が出てしまい、ベチャッとした仕上がりになるので注意してくださいね。
浅漬け・塩もみに合うカット法
キャベツの浅漬けや塩もみには、「繊維を断ち切る細めのざく切り」が最適です。なぜなら、繊維を切ることでキャベツの細胞が壊れやすくなり、塩がなじみやすくなるからです。
作り方としては、幅1.5cmほどのざく切りにして、塩をふって軽くもみ込むだけ。数分で水分が出てしんなりしてきたら、好みの調味料で味付けすれば完成。簡単なのにとても美味しく、あと一品欲しいときに便利です。
また、にんじんやきゅうりなどと合わせても美味しいですし、ごま油や昆布、唐辛子を加えて中華風・和風にもアレンジできます。
キャベツの芯も薄くスライスすれば使えます。葉と混ぜることで食感のバランスも良くなり、捨てずに活用できて一石二鳥です。
切り置きで1週間使えるストック術
毎日キャベツを切るのは面倒……そんな方におすすめなのが、「切り置きストック術」。うまく保存すれば、切ったキャベツを1週間ほど美味しく保つことができます。
まずは千切りやざく切りなど、用途別にキャベツをカット。次にキッチンペーパーで軽く水分を拭き取り、ラップに包むか保存袋に入れて空気を抜きます。ポイントは乾燥と酸化を防ぐこと。
さらに、保存袋に湿らせたキッチンペーパーを一緒に入れると、適度な湿度が保たれて鮮度が長持ちします。冷蔵庫の野菜室で保存すれば、シャキシャキ感もキープできます。
もっと長持ちさせたい場合は、1食分ずつ小分けにして冷凍保存もOK。ただし、解凍後は水分が出やすくなるため、炒め物やお好み焼きなど火を通す料理に使いましょう。
週末にまとめてキャベツを切っておけば、平日のご飯作りがグッとラクになりますよ。
もう失敗しない!キャベツ切り方のよくある疑問Q&A
切る前に洗う?洗ってから切る?
キャベツを使う前に「洗うのは切る前?切った後?」と悩んだことはありませんか?結論から言うと、基本的には切る前に洗うのがベストです。
理由は2つあります。ひとつは、切った後に洗うと、断面からビタミンCなどの栄養が流れ出てしまうため。そしてもうひとつは、切ってから洗うと水分が多く残ってしまい、ベチャっとした仕上がりになりやすいためです。
キャベツは外側の葉を数枚はがして、汚れや農薬が気になる部分だけさっと水洗いすればOK。芯を取った後、切る前に全体を軽く水で流すようにすれば、余分な汚れも落ちます。
どうしても切った後に洗いたい場合は、さっと短時間で洗い、水気をしっかり拭き取ることが大切です。時間があれば、ざるに広げてしばらく自然乾燥させるのも良いでしょう。
包丁がベチャベチャになるのはなぜ?
キャベツを切っていると、包丁がびしょびしょになって切りにくくなることがありますよね。その原因は、「繊維の断ち方」と「包丁の状態」にあります。
キャベツを繊維に逆らって切ると、細胞が壊れて中の水分がどんどん出てきます。これが包丁にくっついてベチャベチャになるのです。特にスライサーや鋭い包丁で細かく切っているときほど、その現象が起こりやすくなります。
また、包丁の切れ味が悪いとキャベツを「押し潰しながら切る」ことになり、余計に水分が出てしまいます。包丁は定期的に研いでおくのが理想。切れ味が良ければ、力を入れずにスーッと切れるので、水も出にくくなります。
ベチャつきが気になるときは、切ったキャベツをキッチンペーパーで軽く押さえる、もしくは水分が多く出にくい「繊維に沿った切り方」に変えると改善できます。
手切りとスライサー、どっちがいい?
手切りとスライサー、どちらを使うべきかは、「何を作るか」と「どれだけ手早く済ませたいか」で決まります。それぞれのメリット・デメリットを見てみましょう。
手切りのメリットは、厚みやサイズを自由に調整できること。料理に合わせて千切り、ざく切り、粗みじんなど細かく使い分けられます。ただし、時間がかかりやすく、包丁に慣れていない人には少し難しいかもしれません。
一方、スライサーは短時間で均一な千切りができるのが最大の魅力。特にサラダや千切りキャベツを大量に使いたいときには便利です。ただし、繊維を無視して切ることになるため、キャベツの水分が出やすくなるというデメリットもあります。
お好み焼きなど、水分が気になる料理には手切りの方が向いています。サラダや浅漬けなど、シャキシャキ感が欲しいときはスライサーでも問題ありません。用途に応じて、うまく使い分けましょう。
冷凍キャベツでも使える?
キャベツは冷凍保存も可能で、使い方を工夫すればお好み焼きにも十分使えます。ポイントは、「冷凍前の処理」と「解凍の仕方」にあります。
まず、冷凍する際はあらかじめ千切りやみじん切りにして、1回分ずつラップで小分けにして冷凍保存するのがおすすめ。これにより、必要な分だけをすぐに使うことができます。
冷凍キャベツは解凍すると水分が多く出るので、解凍後に水気をしっかり絞ることが大事。加熱調理する料理、特にお好み焼きやスープ、炒め物にはぴったりです。
サラダのような生食には不向きですが、火を通す料理ならほとんど違和感なく使えます。価格が安い時にまとめて買って冷凍しておけば、時短にも節約にもなりますよ。
切ったキャベツの保存は水に浸ける?
一部のレシピで「キャベツを水に浸けるとシャキッとする」と書かれていることがありますが、これは正解でもあり、不正解でもあります。状況によって使い分けるのがベストです。
例えば、サラダなどでキャベツのシャキシャキ感を強調したい場合、切った後に氷水に5分ほど浸けることで、細胞が引き締まって食感が良くなります。ですが、長時間水に浸けてしまうと、ビタミンCなどの栄養が水に溶け出してしまうのです。
また、お好み焼きに使う場合は、水分が増えるとベチャっとなりやすいので、基本的には水に浸けないほうがよいでしょう。シャキッと感がほしいときは、切ってから少し冷蔵庫で冷やすだけでも十分です。
つまり、水に浸けるのはシャキシャキを楽しむ生食向け、火を通す料理では不要または避けるのが吉。切った後の処理も料理によって使い分けましょう。
まとめ
キャベツは切り方ひとつで味・食感・栄養・見た目まで大きく変わる、とても奥深い野菜です。特にお好み焼きのようなシンプルな料理では、その違いが顕著に表れます。
千切りにすればふんわりと軽く、粗みじんにすればシャキシャキ感と甘みが際立つ。それぞれの切り方には向き・不向きがあり、「どんな仕上がりにしたいか」に合わせて使い分けることが、お店のような味に近づく第一歩です。
また、切り方によって栄養の残り方も違いますし、保存の仕方によっては1週間分のキャベツを無駄なく使い切ることも可能です。さらに、サラダやスープ、炒め物、浅漬けなど、応用範囲もとても広いです。
包丁の入れ方、切る方向、芯の扱い方、保存テクニックまで、少し意識を変えるだけで、普段の料理がぐっと美味しくなること間違いなし。この記事が、毎日の料理を楽しく、そしてちょっと誇らしく感じられるヒントになればうれしいです。
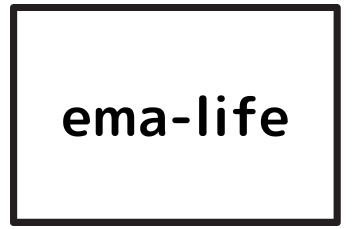
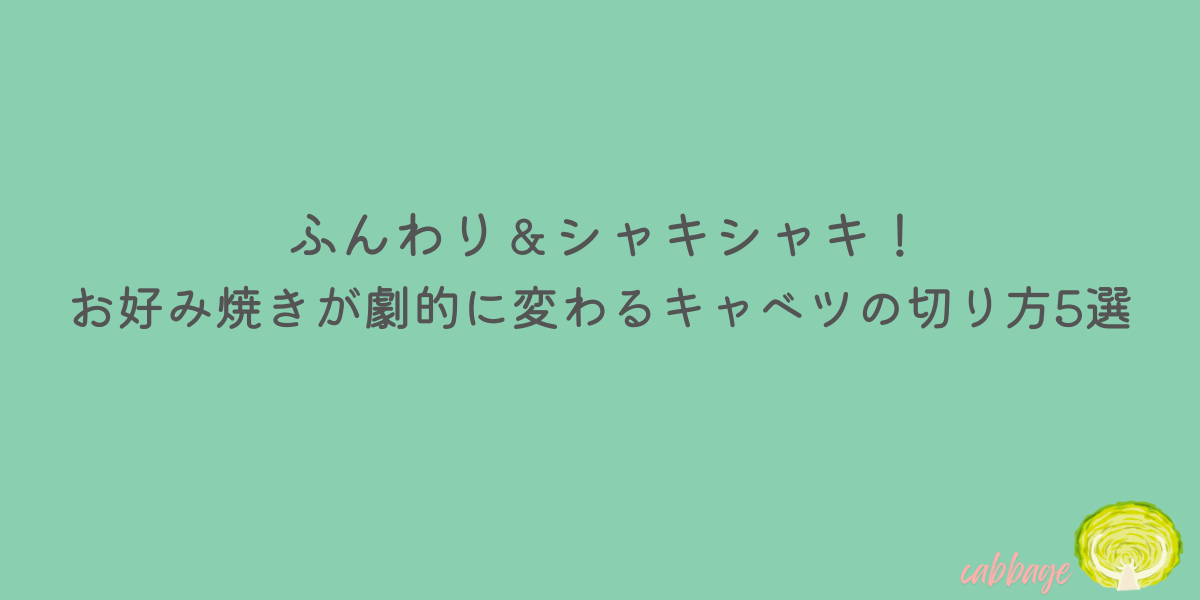
コメント