※当ブログはアフィリエイト広告を利用しています。

「ついていく」って、実は漢字によって意味が違うって知っていましたか? 会話ではあまり気にしないけれど、文章で書くときには注意が必要なんです。
「着いていく」「付いていく」「就いていく」、どれが正しいのか迷ってしまう人も多いはず。この記事では、それぞれの意味の違いや使い分け方を、具体例と一緒にわかりやすく解説します!
簡単に理解できる内容なので、漢字が苦手な人でも大丈夫! 言葉のチカラをもっと味方にしたい人は、ぜひ最後まで読んでみてください。
目次
「ついていく」ってどんな意味?よくある3つの使い方を紹介
会話でよく使う「ついていく」の例
日常の会話でよく耳にする「ついていく」という言葉。たとえば、「お兄ちゃんについていく」「友達についていく」「リーダーについていくよ」など、子どもから大人まで幅広く使われていますよね。この「ついていく」は、簡単に言えば「誰かの後を追って一緒に移動する」という意味で使われるのが一般的です。ただし、この言葉は一見シンプルに見えて、実は文脈によっていろいろな意味を含んでいます。
たとえば、「旅行についていく」と言えば、同行する意味になりますが、「指導者についていく」と言えば、思想や方針に従うという意味にもなります。つまり、「ついていく」という表現は、物理的な移動だけでなく、考え方や感情の面でも使われる柔軟な言葉なのです。
また、「着いていく」と「付いていく」、「就いていく」など、漢字にするとさらに意味が分かれてきます。会話ではあまり意識しないかもしれませんが、正しく書くときにはどの漢字がふさわしいのかを知っておくと、メールやレポートでも恥ずかしくありません。
このように「ついていく」は、日常のさまざまなシーンで使われる便利な言葉であると同時に、日本語の奥深さを感じられる表現でもあるのです。
実は全部同じ意味じゃない?
一見「ついていく」はどの場面でも同じ意味に見えますが、実は細かく分類すると違いがあることが分かります。「物理的に一緒に行く」「行動や考え方を共にする」「場所に到着する」など、似ているようで違う意味を持っています。
たとえば「友達についていく」と「友達と一緒に着いていく」では、どちらも似たような意味に思えるかもしれませんが、「付いていく」は行動を共にする意味で、「着いていく」は目的地に到着するという意味に重きが置かれます。
また、「ついていけない」と言えば、スピードや考え方についていけないという抽象的な使い方になります。このように文脈によって「ついていく」の意味が少しずつ変わってくるのです。
つまり、ただ「ついていく」と言っても、状況に応じて使い分けが求められる表現だということがわかります。
「ついていく」の文法的な分類とは
文法的に見ると、「ついていく」は複合動詞に分類されます。これは、「つく(着く・付く・就く)」という動詞と、「いく(行く)」が組み合わさってできた動詞です。漢字表記が変わることで、意味も微妙に変化します。
・「付く」+「行く」=付いていく(誰かに同行する)
・「着く」+「行く」=着いていく(一緒に目的地に到着する)
・「就く」+「行く」=就いていく(職業などに従事し続ける)
このように、ひとつの動詞が後ろにつくことで、元の動詞のニュアンスが残りながら、新しい意味を持った動詞になります。文法的には、「複合動詞」「自動詞」であることも覚えておくと便利です。
「いく」と「いく(行く)」の違い
「いく」という言葉もまた、表記によって意味が異なります。通常、移動を表すときには「行く」と書きますが、「〜ていく」の形になると、前の動作がこれから先に向かって続くという意味を持ちます。
「ついていく」という言葉においても、「〜ていく」は未来に向けた動作や変化を示しており、たとえば「成長についていく」といえば、その成長のスピードや内容に今後も対応していく、というニュアンスが含まれます。
つまり、「いく」は単なる移動ではなく、変化や進行を伴う表現なのです。これが「ついていく」という言葉に含まれる「追従」「同行」「適応」など、さまざまな意味につながっていくのです。
小学生でもわかる「ついていく」の基本
小学生に教えるときには、まず「ついていく=いっしょに行くこと」と覚えさせるのが一番わかりやすいです。そのうえで、漢字の違いを少しずつ教えていくと理解しやすくなります。
たとえば、
- 「学校についていく」=付いていく
- 「おばあちゃんと病院についていく」=着いていく
- 「先生の仕事についていく」=就いていく
といったふうに、具体的な例を使って説明すると、自然に理解が深まります。言葉の使い方を覚えるだけでなく、漢字の意味も一緒に学ぶことができるので、語彙力もアップします。
「着いていく」「付いていく」「就いていく」の違いとは?
「着いていく」はどんな意味?
「着いていく」は、「目的地に一緒に到着する」という意味を持ちます。たとえば、「友達と駅に着いていく」や「一緒に目的地まで着いていった」という場合に使われます。この場合の「着く」は、「場所に到着する」という意味で、主に移動の終点を示す動詞です。
ただし、「着いていく」は会話ではよく使われる一方で、書き言葉としては少し不自然に見られることがあります。「友達についていく」と言う場合は、「付いていく」の方が一般的で、文法的にも自然な表現とされています。
つまり、「着いていく」は会話や口語表現では自然でも、文書やメールなどでは注意が必要です。
「付いていく」が使われる場面
「付いていく」は、「人や物の後を追って同行する」や「行動や考え方に従う」といった意味で使われる表現です。たとえば、「先生についていく」「流行についていく」「最新の技術に付いていく」などがよくある使い方です。この場合の「付く」は、何かに「くっつく」「従う」という意味合いがあります。
この表現は、物理的な移動だけでなく、抽象的な従属や順応のニュアンスを含むのがポイントです。つまり、「付いていく」は単に誰かと一緒に移動するだけではなく、思想・行動・価値観などにも「従っていく」という意味合いで使われるのです。
また、ビジネスの場面でもよく使われる言い回しです。「上司の意見についていく」「方針についていく」といった具合に、組織の考えや方向性に従って行動することを表す時にも使われます。こうした場面で「着いていく」や「就いていく」と表記してしまうと、意味が大きく変わってしまうので注意が必要です。
とくにビジネスメールやレポートなどの正式な文書では、「付いていく」の漢字が正しく使えているかが、文章の信頼性にも関わってきます。だからこそ、漢字の使い分けは重要なのです。
「就いていく」はまれだけど大切な使い方
「就いていく」という表現は、日常会話ではあまり見かけませんが、正確には「職業や役職に従事する」ことを表す言葉です。「師に就いて修行する」「新しい仕事に就いていく」など、専門性や職業選択の意味合いが強くなります。
「就く」という漢字は、「就職」「就任」などにも使われており、「ある立場や職に身を置く」といった意味を持っています。そのため、「就いていく」は「ある仕事や師匠に従って、その道を歩んでいく」といった、ややフォーマルで深い意味を含んでいます。
特に伝統的な職業や技術職において、「師に就いて〇〇を学ぶ」という表現は今でも使われています。書道や茶道、和菓子職人など、職人の世界ではこの言い回しがよく使われており、日本語の文化的な一面を垣間見ることができます。
つまり、「就いていく」は他の2つとは異なり、単なる移動や同行の意味ではなく、「人生の選択」や「職業への道のり」といった、より重みのある表現なのです。
それぞれの使い方の具体例
ここで、3つの「ついていく」の漢字の違いを具体例で比べてみましょう。以下のように、文脈に応じて使い分けることが大切です。
| 文 | 正しい漢字 |
|---|---|
| 友達のあとを ついていく | 付いていく |
| 目的地に一緒に ついていく | 着いていく |
| 伝統工芸の職人に ついていく | 就いていく |
| 上司の意見に ついていく | 付いていく |
| 東京に一緒に ついていく | 着いていく(口語) |
このように、会話では曖昧に済まされることが多いですが、文章ではしっかり漢字を使い分けることで、相手に正確な意図が伝わりやすくなります。
SNSやメールでの使い方の注意点
SNSやビジネスメールでは、漢字の選び方一つで誤解を生んでしまうことがあります。たとえば、「あなたについていきます」と書いたつもりが、「着いていきます」だと「一緒にどこかに行って到着する」ニュアンスになってしまい、「付いていきます」でないと意図が正確に伝わらないことも。
また、就職活動の自己PRで「この職業についていきたいです」と書いたときも、「就いていきたい」が正解です。「着いていきたい」と書いてしまうと、意味がまったく変わってしまい、評価に影響が出てしまう可能性もあります。
このように、メールやSNSなど文章に残る場面では、文脈に応じた正しい漢字を使うことが非常に重要なのです。
「着いていく」は間違い?正しい使い方とその理由
「着く」と「付く」の意味の違い
「着く」と「付く」は、どちらも「つく」と読みますが、意味が異なります。
| 漢字 | 意味 | 例文 |
|---|---|---|
| 着く | 到着する・身につける | 駅に着く、服を着る |
| 付く | くっつく・従う | ホコリが付く、人に付く |
このように、「着く」は場所や状態に到達することを表し、「付く」は物理的または抽象的に「何かと一緒になる・影響を受ける」という意味があります。
つまり、「着いていく」は「一緒に目的地に到着する」意味でしか使えず、「誰かに従って行動を共にする」意味を表す場合には「付いていく」が正しい表現になります。
なぜ「着いていく」は間違いだと思われがちなのか
「着いていく」は、会話の流れでは自然に聞こえるため、使ってしまう人が多い表現です。しかし、「誰かに同行する」という意味でこの漢字を使ってしまうと、文法的には誤りとされることがあります。
特に国語のテストや作文など、正確な日本語が求められる場面では、「着いていく」は「目的地に到着する」という意味以外では避けた方が良いとされています。
インターネットやSNSでは、「間違った日本語」として取り上げられることもあり、注意を促す投稿も見かけます。これが、「着いていく=間違い」というイメージを定着させている原因かもしれません。
書き言葉と話し言葉での違い
「着いていく」は、話し言葉としては自然に聞こえるため、多くの人が日常的に使っています。しかし、書き言葉になると事情が変わります。文章にすると「目的地に着く」という意味が前面に出るため、「一緒に行動する」「従う」といった意味では違和感を与えてしまうのです。
たとえば、以下の2つの文章を比べてみましょう。
- 話し言葉:「明日、友達に着いていくんだ」
- 書き言葉:「明日、友達に着いていく予定です」
前者は会話として成立しますが、後者は文章として読むと「一緒に目的地に着く」のか「友達に同行する」のか、意味がはっきりしない曖昧な表現になります。
その点、「付いていく」であれば「誰かに同行する・従う」という意味が明確なので、ビジネスメールやレポートなど正確な表現が求められる場面では「付いていく」が適切なのです。
要するに、「着いていく」は会話ではOK、文章では文脈次第で誤解を生む可能性がある表現だと覚えておきましょう。
文法的に正しいのはどれ?
文法的に見たときに、「着いていく」「付いていく」「就いていく」の3つはいずれも誤りではありません。ただし、それぞれが持つ意味と使用される文脈が異なるため、意味に合った漢字を選ぶ必要があります。
日本語の動詞「つく」は、同じ読み方でも「着く」「付く」「就く」など複数の漢字があります。これを同訓異字と呼びます。つまり、読み方は同じでも意味が異なる漢字を使い分ける必要があるのです。
「〜ていく」という形は、動作の継続や未来への進行を示すため、前の動詞の意味をしっかり理解しなければなりません。
- 「場所に着く」→ 着いていく
- 「人にくっついて移動する」→ 付いていく
- 「職に就く」→ 就いていく
このように、それぞれの意味を理解した上で適切な漢字を選べば、どれも文法的に正しい表現として成立します。
漢字の使い分けで印象が変わる!
漢字は、日本語において意味を明確に伝えるための重要なツールです。同じ「ついていく」という音でも、使う漢字が違うだけで相手に与える印象や意味が大きく変わります。
たとえば、ビジネスメールで「プロジェクトに着いていきます」と書いてしまうと、「どこかに一緒に移動して到着する」と解釈されてしまい、本来の意図が伝わらない可能性があります。「付いていきます」と書くことで、「プロジェクトに同行し、貢献する」という意味が正しく伝わるのです。
また、「師匠についていきます」と書く場合も、「就いていきます」と表記すれば、より深い意味で「師匠の元で学びを深めていく」というニュアンスが伝わります。
このように、たった一文字の違いが、相手に伝えるメッセージの重みや方向性を変えてしまうこともあるのです。正しい漢字を使い分けることで、読み手に誤解を与えず、信頼性の高い文章を作ることができます。
実際の例文で学ぶ!「ついていく」の漢字を使い分けよう
学校での「ついていく」
学校での「ついていく」は、小学生から中高生まで頻繁に使う表現です。たとえば「先生についていく」「みんなについていく」など、行動を共にする意味で使われます。こうした場合は、「付いていく」が正しい表記になります。
授業中に「話についていけない」という場合も、「付いていく」が正しいです。ここでは、「内容に追いつく・理解する」という意味が込められているため、「着いていく」では意味が通じません。
一方で、修学旅行などで「バスに乗って着いていく」という文脈では、「着いていく」が自然です。この場合は、「目的地に一緒に到着する」意味での使用です。
このように、学校生活でもシーンに応じた使い分けが求められるため、先生や保護者がしっかりと教えてあげることが大切です。
旅行での「ついていく」
旅行シーンでは、「一緒に行って、同じ場所に着く」という意味で「着いていく」が使われることが多いです。たとえば、「友達に着いていって温泉に行った」という表現は、目的地に到達する意味を含んでいます。
しかし、「ガイドについていく」「ツアーに付いていく」といった表現は、「同行する・一緒に行動する」という意味なので、「付いていく」が正解になります。
旅行では「移動」と「同行」が混ざるため、漢字の選び方一つで意味が微妙に変わります。特に旅程の説明やブログ記事、旅行記などでは、正しい漢字を使うことで読者の理解を深めることができます。
ビジネスシーンでの「ついていく」
ビジネスでは、「方針についていく」「上司についていく」「技術の進化についていけない」などの表現が頻繁に登場します。これらはすべて「付いていく」が正しい使い方です。
一方で、「現場まで一緒に着いていく」という場合は、「着いていく」が適切になります。特に報告書や議事録では、「誰がどこに行ったのか」を正確に伝えるためにも、漢字の違いは無視できません。
「就いていく」は、たとえば「先輩に就いて学ぶ」「この分野に就いていきたい」といったように、キャリア形成や技術習得に関係した文脈で使われます。堅めの表現ですが、説得力を高める場面では効果的です。
ビジネス文書では、誤解のない漢字選びが信頼性を高めるカギになります。
(続きます:次は「メールやチャットで正しく使うには」から執筆します)
メールやチャットで正しく使うには
現代では、仕事やプライベートを問わず、メールやチャットを通して人とやり取りする機会が非常に多くなりました。そんな中で、「ついていく」という表現を使う場面も少なくありません。たとえば、「〇〇さんに付いていきます」「現地には〇時に着いていきます」「その分野に就いていきたいです」など、場面によって使う漢字は異なります。
まず重要なのは、漢字の使い分けによって伝えたい意味が明確になることです。たとえば、上司や先輩に同行する場合、「〇〇さんに着いていきます」と書くと、「一緒にどこかに到着する」という印象を与えてしまいます。しかし、「〇〇さんに付いていきます」であれば、「行動を共にする・従う」という意味がはっきりと伝わります。
一方、「現地に〇時に着いていきます」という場合には、「着いていく」で問題ありません。このときは、「時間通りに現地へ一緒に到着する」ことを表しているからです。
チャットやLINEのような気軽なツールでは、ついひらがなで「ついていきます」と書いてしまいがちですが、ビジネスの場では漢字の違いが信頼性にも関わってきます。特に取引先や目上の人とのやりとりでは、正しい漢字を選ぶことで誠実さや文章力もアピールできるのです。
このように、メールやチャットでは「相手に誤解されない」「意図が正確に伝わる」ことを意識して、場面に応じた漢字を選ぶように心がけましょう。
クイズ形式で復習しよう!
最後に、これまで学んできた「ついていく」の漢字の使い分けをクイズ形式でおさらいしてみましょう。以下の文の( )に入る正しい漢字を選んでみてください。
Q1. 彼の後を( )いったら、道に迷わずにすんだ。
→ A. 着いて B. 付いて C. 就いて
Q2. 新幹線で一緒に( )いく予定です。
→ A. 着いて B. 付いて C. 就いて
Q3. 有名な職人に( )修行を積んだ。
→ A. 着いて B. 付いて C. 就いて
Q4. 時代の変化に( )いくのが難しい。
→ A. 着いて B. 付いて C. 就いて
Q5. 明日の商談にも( )いきますので、よろしくお願いします。
→ A. 着いて B. 付いて C. 就いて
正解:
Q1 → B. 付いて
Q2 → A. 着いて
Q3 → C. 就いて
Q4 → B. 付いて
Q5 → B. 付いて
このように、文脈を正しく理解することで、どの漢字を使えば良いかが自然と分かるようになります。ぜひ、この記事をきっかけに日本語の奥深さと面白さを感じてみてください。
まとめ:「着いていく」の正しい使い方をマスターしよう
漢字の使い分け早見表
これまで紹介した内容を一目で確認できるように、以下のような早見表を作成しました。
| 用例 | 意味 | 正しい漢字 |
|---|---|---|
| 一緒に移動する・同行する | 付いていく | ✅ 正解 |
| 目的地に到着する | 着いていく | ✅ 会話で自然、書き言葉では注意 |
| 職業や師匠に従事する | 就いていく | ✅ 専門的な表現 |
この表を見れば、どの表現がどんな意味で使われるのか、すぐに判断できます。プリントして壁に貼っておいても便利かもしれませんね!
よくある間違いをチェック
- 「上司に着いていきます」→ ❌「付いていきます」が正解
- 「新しい技術に着いていけない」→ ❌「付いていけない」が正解
- 「弟と一緒に駅に付いていきました」→ ❌「着いていきました」が正解
このように、よく使うからこそ間違いやすい表現です。「誰に?」「どこへ?」「どんな関係性で?」という視点を持てば、間違いを防ぐことができます。
文章力がアップする漢字選びのコツ
文章を書くときに「なんとなくの感覚」で漢字を選んでいませんか? それでは誤解される文章になることもあります。大切なのは、意味にふさわしい漢字を正しく使うことです。
たとえば、「誰かに従う」場合は「付いていく」ですが、「どこかへ一緒に行く」なら「着いていく」です。こうした微妙な違いを意識することで、あなたの文章は格段に読みやすく、伝わりやすくなります。
中学生でも迷わない日本語の使い方
この記事では、中学生でも理解できるような表現で「ついていく」の使い分けを説明してきました。なぜなら、言葉は早いうちに正しく覚えることが大切だからです。
国語の授業や作文、将来のレポートやビジネスメールでも役立つ「言葉の知識」を今のうちから身につけておくことで、将来の自信にもつながります。
日本語の面白さを楽しもう!
日本語には、同じ音で意味が違う言葉(同訓異字)がたくさんあります。その中でも「ついていく」は、意味の違いがはっきりと表れる良い例です。日常的に使う言葉だからこそ、正しい使い方を知っておくことで、言葉の力をもっと味方にできます。
「ただ話す」だけでなく、「正確に伝える」力がつくことで、あなたのコミュニケーション力も自然とアップします。日本語の面白さを、これからも一緒に楽しんでいきましょう!
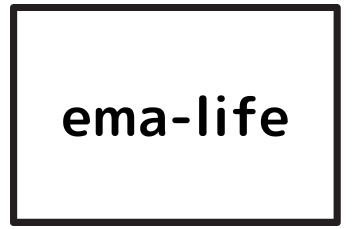
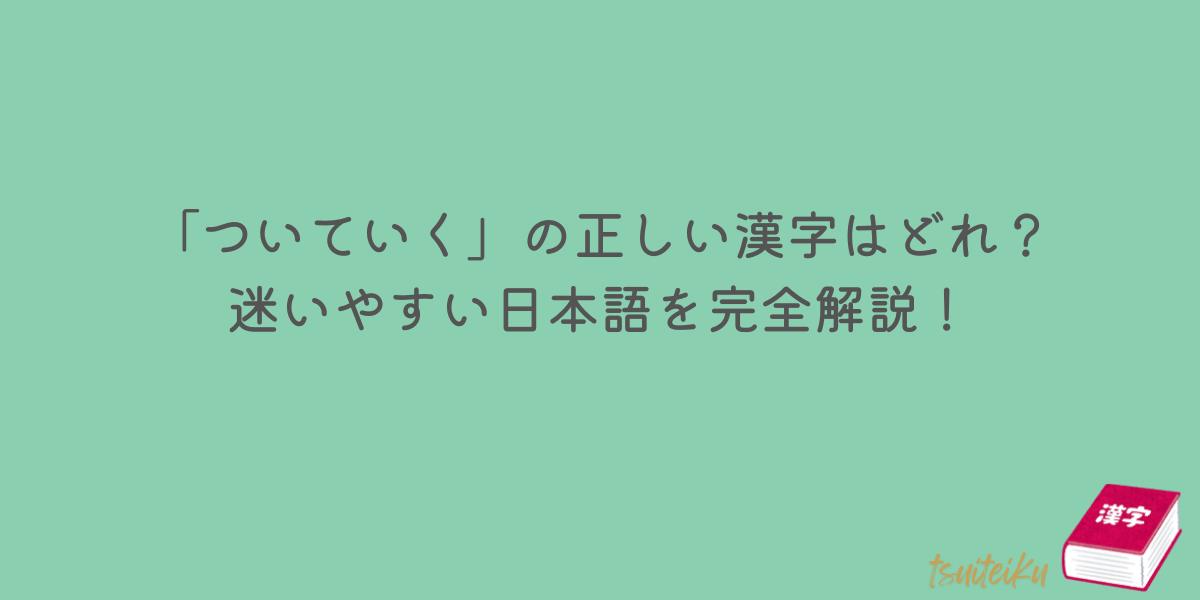
コメント